戦国武将 (中公文庫)
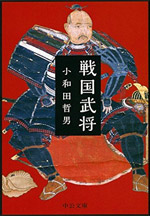 戦国武将 (中公文庫) 小和田 哲男(著)
戦国武将 (中公文庫) 小和田 哲男(著)
「戦国時代」とはいったいどういう時代だったのかを、戦国武将・家臣・家族などを取り巻くさまざまな背景(身分、出自、謀叛、文武、死生観など)から検証した本(1981年刊行)。著者の小和田氏はNHK大河ドラマ「秀吉」「功名が辻」「天地人」「江~姫たちの戦国~」「軍師官兵衛」の時代考証を担当されているそうです。
戦国時代は、小説・ドラマ・映画などの創作的イメージも強く、特に子どものころははるか昔のおとぎ話ぐらいの感覚でいましたが、でもよく考えたら”たった”400~500年前のこと。創作という観点ではなく、著者による具体的な資料分析からその時代を掴むことができ、当時の”時代の全体像”という知識欲を満たしてくれる内容です。文体もとてもわかりやすい。
興味深いテーマ、面白かったところ箇条書き。
・当時の人々は「戦国」という意識を持っていたのかどうか
・家筋より器量、権威より実力というあたらしい秩序が生まれた
・器量のない者は主君であっても排除(下克上)
・合理主義の体現者が戦国時代を勝ち抜いた
・身分は流動的だった
・戦国大名のほとんどは同列の国人領主の中から一人担ぎ出され押し立てられた
・秀吉は百姓出身だが、どんな立場(階層)の百姓だったのか
・百姓から武士への転化がどうして可能だったのか
・天下を取るまでと、天下をとってからの方策は違う
・ぶどう一房=戦国大名の領国。一粒一粒が戦国大名の部将
・外様や国衆は戦国大名に攻められ降伏したり屈服を余儀なくされた
だから、心底服従する気にはなれない
・戦国大名の家臣は、主従関係を続けるも破棄するも自由「去就の自由」
・仕えた主家が弱ければ、主家の滅亡などによって転々としなければならない
・女性や子どもたちは政治上のかけひきにおける政略の道具
・仮に10人の兄弟がいるとしたら、そのうち2~3人しか生き残らないのが戦国時代
・死は当たり前。どう死ぬか、いかにカッコよく死ぬかが美学
・父の壮烈な死で子が優遇
・名誉ある死に対する、不名誉な生
・武将が和歌に嗜みを持っていたのは、辞世を残さない=恥と思っていたから
武将本人よりも家臣や家族に比重を置いているのがよかったです。大河ドラマを見ていても、武将との関わり合いはとても興味の湧くところ。この本のおかげでこれからの大河ドラマなどの歴史モノをより楽しむことができそうです。