信長・秀吉・家康の研究
黒田官兵衛が大河ドラマの主役に選ばれた理由として、歴史の「舞台裏」を知りたいというニーズを汲み取ったとのことですが、直近の「江」「八重の桜」「軍師官兵衛」と日本史上では主役扱いでない人を中心に据えたストーリーはどれも興味深く、また「平清盛」であっても、副読本として『経営者・平清盛の失敗』などを読んだりと、異なるレイヤーから歴史をみつめるというのが仕事以外の知識欲として一番大きい今日このごろ。
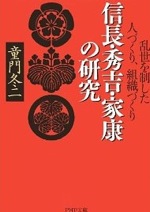 さて、官兵衛周辺をおさらいするために、家にある戦国乱世系書物をいくつか引っ張りだし、6年前の正月休みに読んだ「信長・秀吉・家康の研究」を再読中。
さて、官兵衛周辺をおさらいするために、家にある戦国乱世系書物をいくつか引っ張りだし、6年前の正月休みに読んだ「信長・秀吉・家康の研究」を再読中。
![]() 信長・秀吉・家康の研究 童門冬二 (著)
信長・秀吉・家康の研究 童門冬二 (著)
信長・秀吉・家康の三英傑がどのようにして天下を制したのかを、人づくり・組織づくりという観点で考察しています。旧価値観を破壊した信長、新価値社会を建設した秀吉、新価値社会を修正改良しながら維持した家康。時代背景のなかで違った目的をもった3人の人づくり・組織づくりに体する手腕やエピソードはなかなかエキサイティング。
たとえば、リーダー自らが率先して危地へ乗り込んで行く「ここへ来い」方式が当たり前の時代に、部下が喜んでそこへ行くようにモラルアップする「あそこへ行け」方式に変えたのが信長だといいます。いま自分がやらなければいけないことに当てはまるなぁ…。久しぶりに読み返してみて、刺さるところが変わってきました。きっとこの先、5年後10年後もいろんな発見がありそうな本なので殿堂棚に入れておこう。
ちなみに、最後の章にリーダーを支えた蒲生氏郷、黒田如水(官兵衛)ら名参謀らが何人か紹介されていて、ドラマと並行して読むにちょうどよいです。